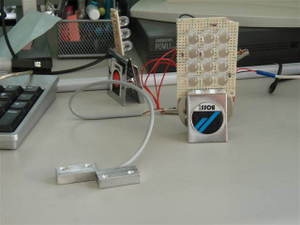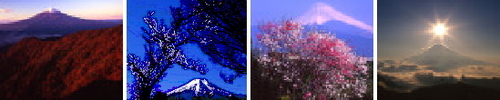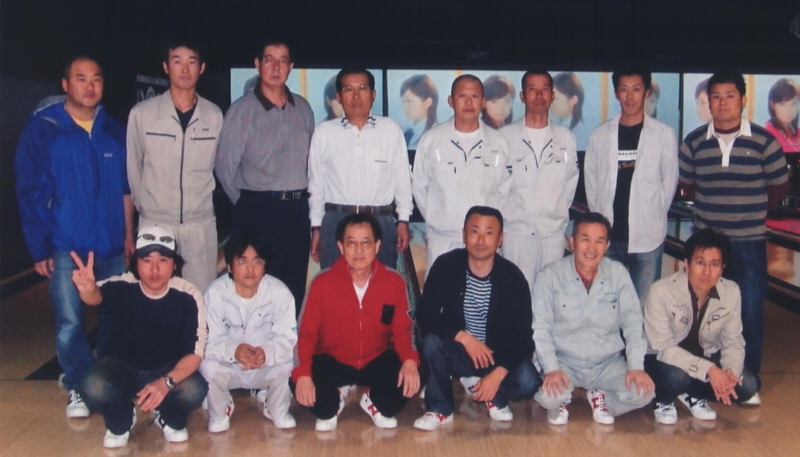ボンド,ベトン・ボンド。
先週に引き続き,構造体コンクリートのお話しが続きます。
梅の花がほころび始めた頃のある日,ある会社で突然,電話がなりました。
“ トゥルル・トゥルル ”
「 ○○生コンですが 」
『 **建設のS現場ですが。2月○日,お宅で打ったコンクリートのD養生の強度が呼び強度を下回っているんですけどね 』
「 へっ? D養生? まぁ現水養生ですから,呼び強度を下回ることもありますよ。今年の冬は,新年明けてから寒い日が続きましたから 」
注) D養生とは,供試体の養生方法を表す符号で,この場合,現場水中養生を指します。また,現場水中養生
とは,現場で打設されたコンクリートに近い状態で養生して,構造体の強度を推定する方法です。
『 でもぉ,呼び強度30で注文したのに,強度が30N/㎜2より低ければお金払いたくないけどね。まぁ,理由を報告書に纏める等して説明してもらえませんか?』
「 §#£¢$……… 」
“ ガチャン・ツー・ツー ”
さて,みなさんは,このようなやり取りをどのように考えますか。
また,このような電話を受けたら,どのように回答しますか?
ここで,状況を簡単に説明します。
注文されたコンクリートと強度結果はつぎのとおりです。
・ 呼び強度 30
・ 現場代行業者による圧縮強度結果 現場水中養生強度 材齢28日 29.7 N/㎜2
・ 同日採取した生コン工場の圧縮強度試験結果 標準水中養生強度 材齢28日 34.1 N/㎜2
施工者(あるいは設計者)は,生コン会社(あるいは生コン協組)に呼び強度30のコンクリートを注文しています。コンクリートの打設した時期から推定すると,所要の設計値は次のようになります。
・ 設計基準強度(Fc) : 21 N/㎜2
・ 構造体コンクリートと供試体の強度との差を考慮した割増し(⊿T) : 3 N/㎜2
・ 予想気温による強度の補正値(T) : 6 N/㎜2
今回,施工者は,現場代行試験業者に構造体コンクリートの管理を依頼しています。
先週のお話しを少し復習しましょう。
JASS5より
【使用するコンクリート】
1)養生方法 : 標準水中養生
2)管理基準 : 材齢28日における3回の試験結果の平均値 ≧ Fc+⊿T+T
材齢28日における3回の試験結果の最小値 ≧ 0.85×(Fc+⊿T+T)
【構造体コンクリート】
1)養生方法 : 現場水中養生
2)管理基準 : 材齢28日における3回の試験結果の平均値≧Fc+⊿T
Fc : 設計基準強度
⊿T : 構造体コンクリートと供試体の強度との差を考慮した割増し
T : 予想気温による強度の補正値
**建設S現場での現場代行業者の圧縮強度試験値は,
“ Fc+⊿T=21+3=24 N/㎜2以上 ”で判定すればよいのですから,○○生コンのコンクリートは,JASS5の管理基準に適合しています。
また,同日に同現場で,○○生コンが採取したコンクリートは,標準水中養生で呼び強度以上ですから,使用するコンクリートについてもJASS5に適合していると思われます。
先の電話を受けた○○生コンは,**建設S現に次のような説明を行いました。
・ 標準水中養生圧縮強度は,呼び強度以上であり,現場水中養生圧縮強度もFc+⊿T以上であるため製造したコンクリートに異常はない。
・ 打設後の外気温が低く,現場水中養生強度が影響を受けた。
提出書類
① 呼び強度30の製品試験(標準水中養生圧縮強度)実績から作成した管理図の提出
② 打設日から数日間の外気温の記録(最高温度は平均5℃,最低温度は1℃)
説明を受けた**建設S現場の工事担当者は,構造体コンクリートが管理基準に適合することに安心しているようだったが,現場水中養生強度が呼び強度30を下回ったことを気にしておりました。
例えば,外気温が高い夏期は,現場水中養生強度が呼び強度を超えます。しかし,コンクリートを製造するうえでは,外気温の変動に対して,強度を保証することは不可能です
**建設は,一部上場企業かつスーパーゼネコンですが,この工事担当者は,コンクリートについてあまり知識がない様子です。
最近,工事現場で従事している従業員は,ゼネコン所属ではなく派遣社員の方が増えていると伺うことがあります。
このためかどうかは定かではありませんが,工事現場で働いている人が,かならずしもコンクリートのことを理解しているわけでないということです。
管理基準さえ理解しているとはいえない施工者から,コンクリートの注文を受けることに多少疑問があります。
しかし,私たち生コン製造者も高品質の建物を造る責任の一部を担っているのですから,仕様書(コンクリート標準示方書やJASS5)を把握することは,必要であり重要だと思われます。
また,仕様書を理解することで,不本意なクレーム(クレームではない現場からの苦情等)を無難に回避することができることがあります。
さて,2週にわたり構造体コンクリートについて説明しましたが,残念ながらまだ不十分です。
次週もしつこくこのお話は続きます。
激しい雨がふった週末でした。
蒸し暑い日はきらいです。 -ベトン・ボンド-